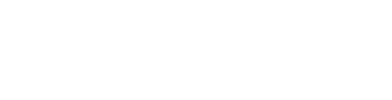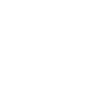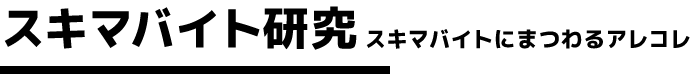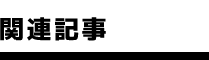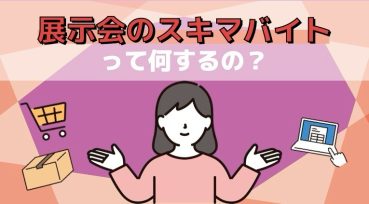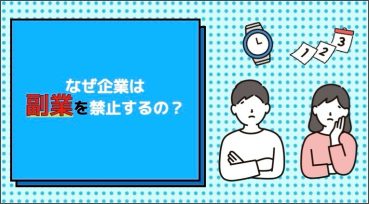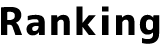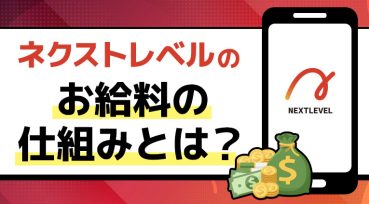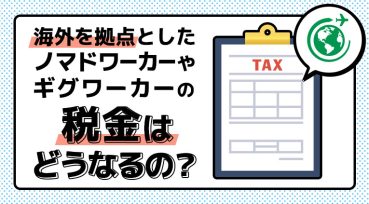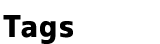パート・アルバイトの住民税はいくらから?
25.04.15
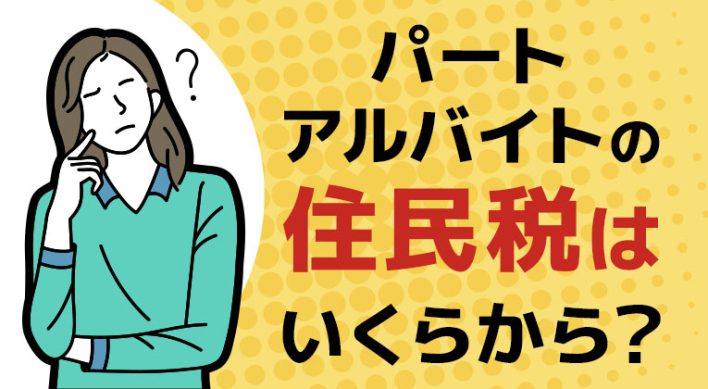
パートやアルバイトをしている方の中には、「自分の収入で住民税が発生するのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。住民税は、一定の収入を超えた場合に支払う義務が生じる税金です。
本記事では、住民税の仕組みや計算方法、納税方法について詳しく解説します。自分の収入が住民税の対象になるかどうか、しっかり確認しておきましょう。

住民税の課税の仕組み
まずは、住民税の仕組みについて理解を深めましょう。
住民税とは?
住民税とは、都道府県や市区町村に納める税金であり、公共サービスの提供や地域のインフラ整備などに使われます。会社員や個人事業主はもちろん、一定以上の収入があるパート・アルバイトの方にも課税されます。
なお住民税には、以下の2種類があります。
- 均等割:所得に関係なく、一律で課税される部分(自治体により異なるが、一般的に年間5,000円程度)。
- 所得割:年間の所得に応じて課税される部分(税率は自治体ごとに異なり、一般的に10%前後)。
住民税が発生する収入の目安
住民税は、以下の条件を満たすと課税対象になります。
- 扶養されていない人(単身者など):年間所得が 100万円超 の場合、住民税が発生する可能性があります。
- 扶養されている人(学生・主婦など):年間所得が 98万円超 の場合、住民税が発生する可能性があります(自治体により多少の違いあり)。
ただし、自治体ごとに非課税限度額が異なるため、正確な金額は居住する市区町村のホームページで確認しておきましょう。
住民税のシミュレーション例
具体的な金額がイメージしやすいように、年収別に住民税をシミュレーションしてみましょう。
年収100万円未満
所得控除の範囲内であり、基本的に住民税はかかりません。
ただし、自治体によっては均等割(約5,000円)が発生する可能性があります。
年収120万円
課税所得:約120万円-55万円(基礎控除)=65万円
住民税(10%として計算):65万円×10%=65,000円
均等割(約5,000円)を加えると、合計70,000円程度の住民税がかかる可能性があります。
年収150万円
課税所得:約150万円-55万円(基礎控除)=95万円
住民税(10%として計算):95万円×10%=95,000円
均等割(約5,000円)を加えると、合計100,000円程度の住民税がかかる可能性があります。
※計算例は概算です。実際の税額は自治体や各種控除により異なります。
住民税の納税方法
住民税の納税方法には以下の2種類があります。
1. 特別徴収(給与天引き)
会社に雇用されている場合、住民税は給与から自動的に天引きされ、会社がまとめて自治体に納めます。これを「特別徴収」といいます。
- メリット:自分で納付の手続きをする必要がなく、支払いの手間がかからない。
- デメリット:住民税を払っていることが勤務先に分かるため、副業がバレる可能性がある。
2. 普通徴収(自分で納付)
フリーランスや個人事業主、パート・アルバイトで一定の条件を満たす場合は、自治体から納付書が届き、自分で住民税を納めることになります。
- メリット:会社に住民税の支払いを知られることがない。
- デメリット:自分で納付しなければならず、支払いの管理が必要になる。
納税は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて支払うことが一般的です。一括払いも可能ですが、負担を分散したい場合は、分割納付で支払いましょう。
自治体によっては最近、クレジットカード払いやスマートフォン決済アプリなどでも支払いができるようになりつつあります。
住民税の仕組みを理解して、適切な対応を

パート・アルバイトの方でも、一定以上の収入がある場合は住民税の支払いが必要になります。目安として、年収100万円以上(扶養内なら98万円以上)で住民税が発生する可能性があるため、支払い漏れのないように自分の収入状況をしっかり把握しておきましょう。
また、住民税の支払い方法には「給与天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。会社に知られたくない場合は、普通徴収を選択するのも一つの方法です。
住民税は自治体ごとに異なるため、詳細な金額や計算方法は居住する市区町村の公式ホームページで確認することをおすすめします。また、市役所の窓口でも確認や相談に応対してくれるため、疑問点があれば足を運んでみるのも良いでしょう。
賢く住民税を管理し、安心して働きましょう!